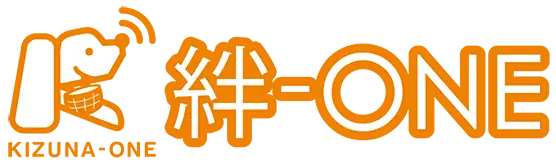ブログ
ブログ
マンション経営者のための個人の孤独死保険とは?種類や選び方についても解説
1.孤独死保険とは?その重要性

1.1.孤独死保険とは
孤独死保険とは、賃貸住宅の入居者、個人が孤独死した際に発生する費用やリスクを保証するための保険です。特にマンション経営者にとっては、入居者が孤独死した際の対応や費用負担が問題となります。孤独死により生じる主な金銭的な負担は部屋の清掃や消臭作業かかる費用や遺品の型付けにかかる費用、空室や家賃引き下げによる損失などが発生します。この保険は、そのようなリスクを軽減するための重要な手段です。孤独死保険は、家主型と入居者型の大きく二つの種類に分かれており、それぞれの特徴やメリットを理解することが重要です。

1.2.マンション経営者にとってのリスク管理
マンション経営者にとって、孤独死のリスクは無視できません。入居者が孤独死した場合、その後の対応には多くの手間と費用がかかります。例えば、遺品整理や清掃、場合によってはリフォームが必要となることもあります。さらに、次の入居者を見つける際には、物件のイメージが悪化する可能性もあります。これらのリスクを軽減するための方法として、孤独死保険への加入が有効です。孤独死保険は、これらの費用をカバーし、経営者の負担を軽減します。

2.孤独死保険の種類と選び方
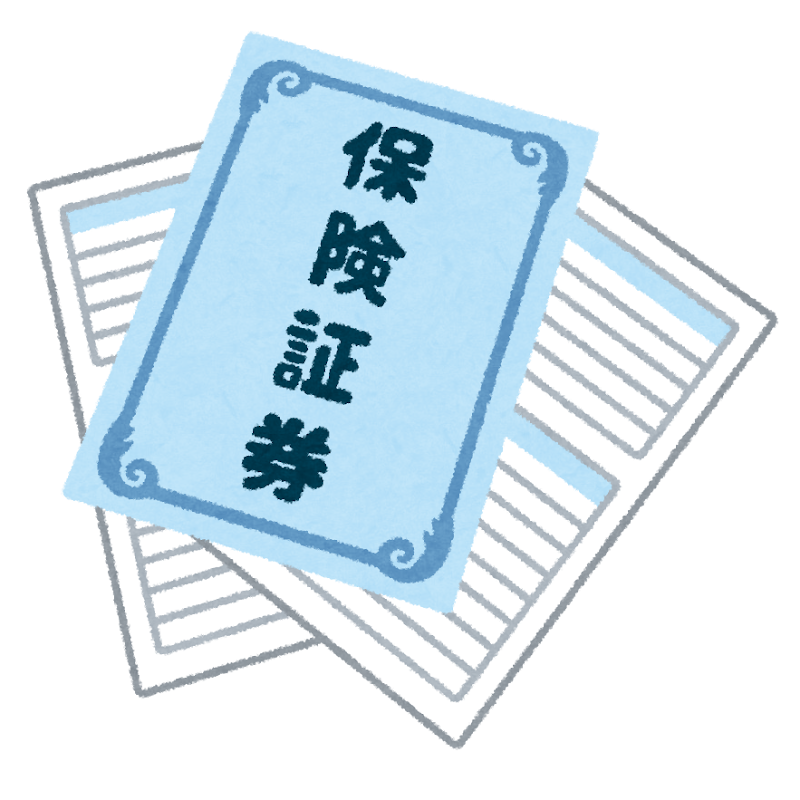
2.1.家主型孤独死保険とは
家主型孤独死保険は、マンションやアパートに対する保険です。なので、契約者は入居者ではなく、所有者になります。保険加入対象の部屋で、孤独死(保険会社により、「自殺」や「事件」もカバーできる保険もあります)が原因により、遺品整理費用や清掃費用、リフォーム費用、損失家賃などの費用を全額または一部を保険で補償することが出来ます。家主型孤独死保険の補償内容には3つあります。
(1)遺品整理費用・・・業者に依頼した場合発生する費用。残置物処理費用とも呼ばれる。
(2)原状回復費用・・・再び賃貸できるようにするための作業を業者に依頼した場合発生する費用。清掃、消臭作業、畳の張り替えなど。
(3)家賃保障費用・・・孤独死があった部屋や隣の部屋で空室が続いた場合の家賃や、
家賃を減額しなければならなかった場合の損失額に一部または全額。
保険料の相場は1室につき月額数百円です。月に数百円と考えると、とても安く感じますが、実際に支払う保険料は、1棟単位が原則ですので、契約内容により決められた保険料×1棟の室数が月額の保険料になります。1室単位でのピンポイントでの契約が出来ないので、コストが高くなる傾向にあります。
2.2.入居者型孤独死保険とは
入居者型孤独死保険は、マンションやアパートの入居者が加入する保険です。なので、契約者は、入居者となります。入居者の孤独死が起因による費用やリスクをカバーします。この保険では、遺品整理費用や清掃費用だけでなく、家族や親族に対する補償も含まれることがあります。入居者型孤独死保険は、入居者自身の安心感を高めるための手段として有効です。「入居者型孤独死保険」の保険料の相場は、1室につき月額300円程度です。年間で、3600円程度になります。入居者型孤独死保険は単独の保険として契約するのではなく、賃貸住宅に入居する際に加入する「家財保険の特約」として加入するケースが一般的です。ただし、孤独死による家賃減額補償や空室期間家賃補償はカバーできません。また、保険請求は、入居者の相続人が行うことが原則です。もし、相続人が居ない場合は、保険金請求が出来ないことになります。ただし、保険の特約において、大家さんや管理会社が保険金請求できるものもあるので確認して頂くことをお勧めします。

2.3.保険選びのポイントと注意点
孤独死保険を選ぶ際には、以下のポイントに注意することが重要です。
(1)保険料と補償内容のバランス
保険料が安いからといって、補償内容が不十分であれば意味がありません。しっかりと補償内容を確認し検討していきましょう。
(2)特約やオプション
必要に応じて特約やオプションを追加することで、補償内容を充実させることができます。しかし何でもかんでも追加するのではなく、本当に必要なものか重複は生じていないかまで確認をおこないましょう。
(3)保険会社の信頼性
信頼性のある保険会社を選ぶことも重要です。そのため口コミや評判を確認しましょう。また実績や登録者数なども検討する1つの手段です。
(4)保険金の支払い条件
保険金の支払い条件や手続きが複雑でないか確認しましょう。

3.孤独死保険の費用と保険料の比較
3.1.家主型と入居者型の保険料の違い
家主型孤独死保険と入居者型孤独死保険では、保険料の設定が異なります。家主型は物件全体を対象とするため、保険料が高めに設定されることが一般的です。一方、入居者型は個人単位での加入となるため、比較的保険料が安く設定されることが多いです。また、補償内容や特約の有無によっても保険料が変動します。それぞれの保険のメリットとデメリットを理解し、自分に合った保険を選びましょう。
3.2.費用対効果の考え方
孤独死保険の選択に際しては、費用対効果を考慮することが重要です。単に保険料が安いからといって、それが最適な選択とは限りません。補償内容が充実しているか、実際に役立つ場面が多いかを確認することが大切です。例えば、遺品整理や清掃、リフォームにかかる費用をカバーしてくれる保険であれば、万が一の際に大きな助けとなります。また、特約やオプションを追加することで、さらに充実した補償を受けることができる場合もあるため、総合的に判断しましょう。

4.孤独死保険の加入手続きと条件
4.1.加入手続きの流れ
孤独死保険に加入する手順は、一般的に以下の流れとなります。
(1)保険会社の選定
まずは信頼できる保険会社を選びます。
(2)見積もりの取得
保険会社に見積もりを依頼し、保険料や補償内容を確認します。
(3)申込書の記入
加入を決定したら、申込書に必要事項を記入します。
(4)必要書類の提出
身分証明書や物件の情報など、必要な書類を提出します。
(5)保険会社の審査
保険会社が申込内容を審査し、承認されれば契約が成立します。
(6)保険料の支払い
初回の保険料を支払い、保険が開始されます。
4.2.加入条件と必要書類
孤独死保険に加入するための条件や必要書類は、保険会社によって異なりますが、一般的には以下のようなものが必要です。
(1)身分証明書
運転免許証やパスポートなどが求められます。
(2)物件の情報
物件の所在地や規模、所有者の情報などが必要です。
(3)健康状態の確認
一部の保険では、加入者の健康状態に関する情報が求められることがあります。
(4)その他の書類
保険会社が指定するその他の書類が必要な場合があります。事前に確認し、必要な書類を準備しておきましょう。

孤独死対策としての見守りサービス
5.1.人感センサーでの見守りサービスの紹介
孤独死対策として、近年注目されているのが人感センサーを活用した見守りサービスです。人感センサーは、部屋の中での人の動きを検知し、一定期間動きがない場合にアラートを発する仕組みです。このサービスを利用することで、入居者の異常を早期に発見し、迅速な対応が可能となります。特に高齢者や一人暮らしの入居者に対しては、大きな安心感を提供することができます。
5.2.見守りサービスと孤独死保険の併用がおすすめ
見守りサービスと孤独死保険を併用することで、さらなる安心感を提供することができます。日頃、人感センサーで見守り、異常の早期発見を行います。万が一、孤独死が発生し、損害が発生しても保険でカバーできます。これにより、見守りサービス単体や保険単体よりもダブルで対策を行った方がより安心で負担が少なく済みます。また、保険会社によって、お部屋に人感センサーを設置することを条件に、1室単位で保険加入が出来るものもあります。これにより、孤独死の発生率が少ない、複数人世帯やファミリーのお部屋を保険対象外とすることが出来、必要なお部屋のみ保険加入が出来るようになります。ですので、人感センサーでの見守りサービスと保険を組み合わせて対策をすることにより、より安心で負担の少ない対策が可能となります。
【まとめ】
マンション経営者の立場で検討される可能性がある個人の孤独死保険について、種類や選び方についてご紹介しました。賃貸契約に伴うリスクを低減するツールとして活用して頂く一助になれば幸いです。